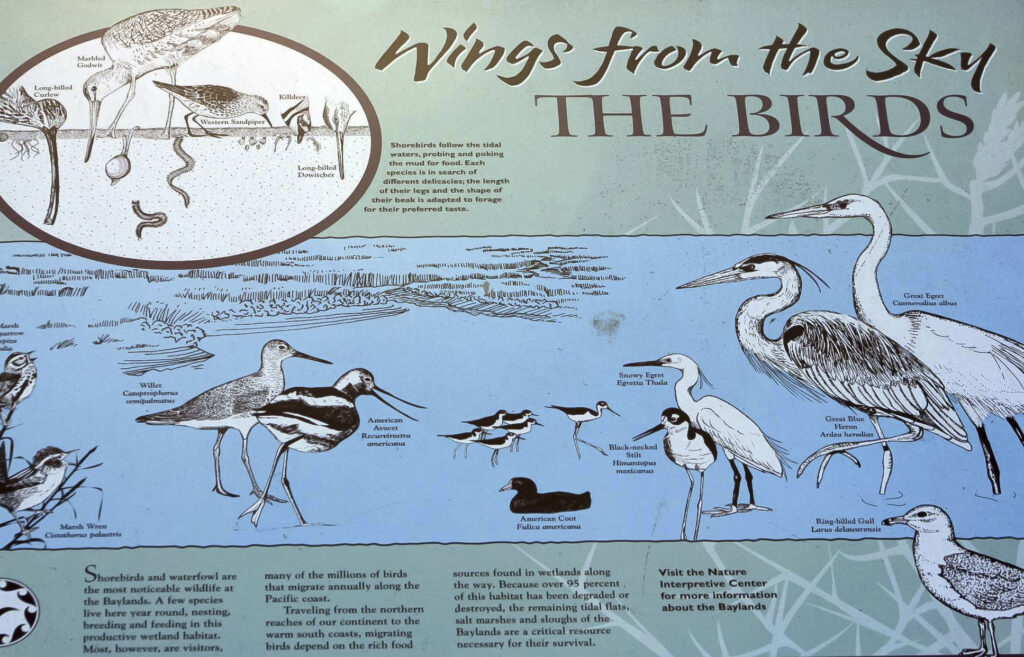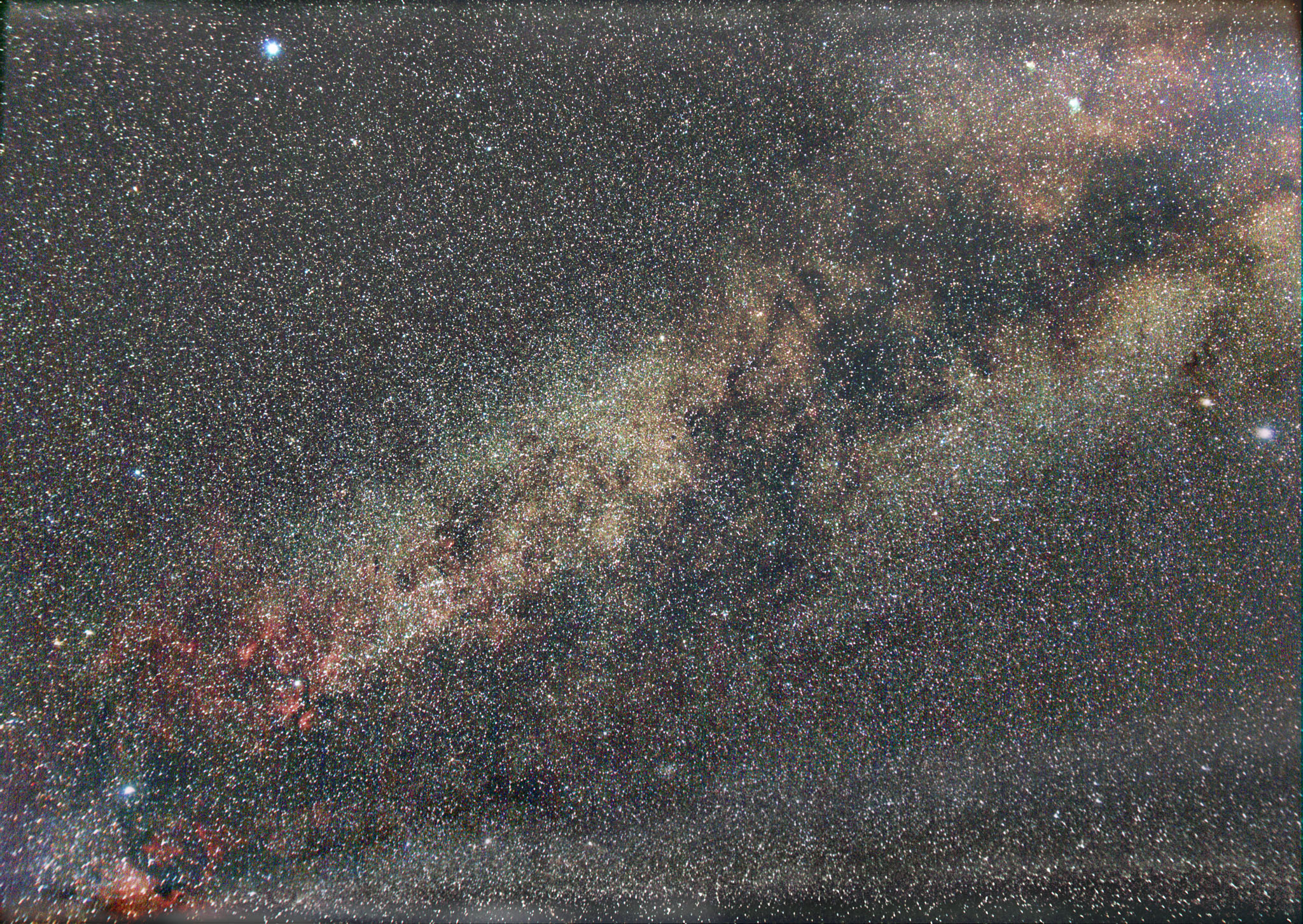2025/3/20~21 from Sunnyvale California
Newtonian reflector of 250mm diameter with 1000mm focal length on CGEM with Quattro coma corrector, controlled by CPWI without autoguiding,
filtered by Svbony SV220
Lights: 300 x 15 secs, Darks: 30, Flats: 30 were taken with ZWO ASI294MC PRO.
Software:
SharpCap
Gain=420, Exposure=15,
White Bal (B)=95, White Bal (R)=52
Brightness=39, Gamma=94, Temperature=2.5
DSS, Noise Ninja, GraXpert, GradientXTerminator, Photoshop CS5